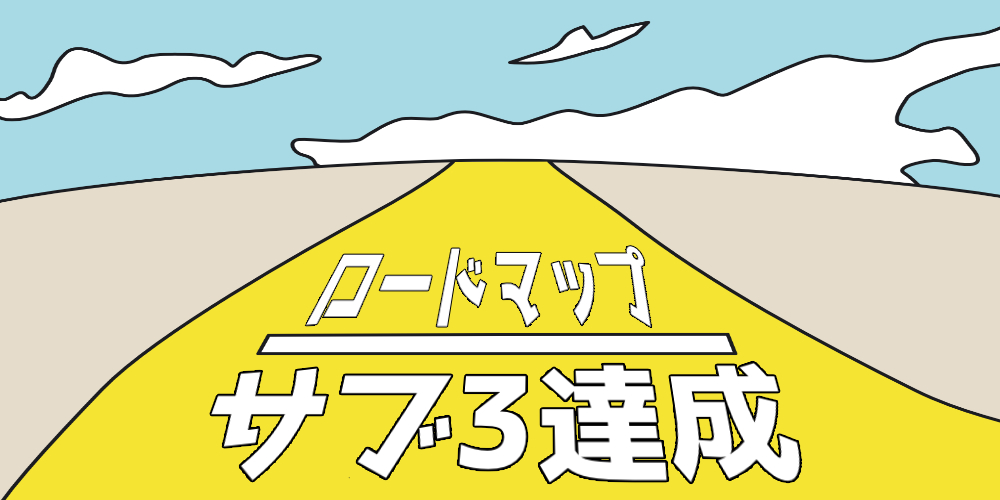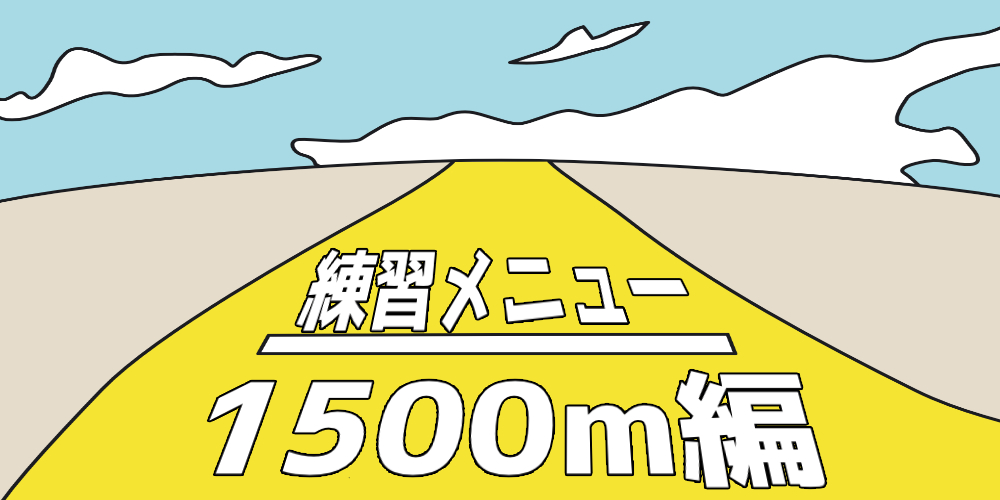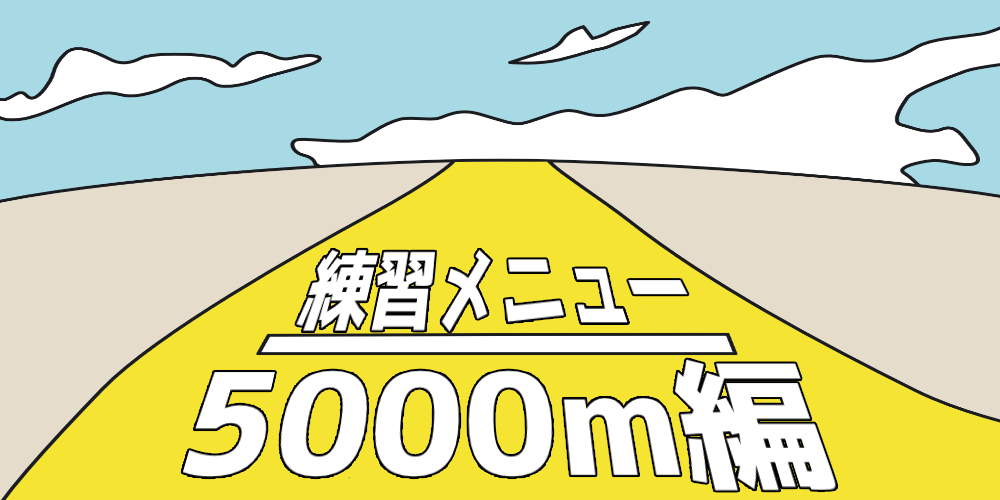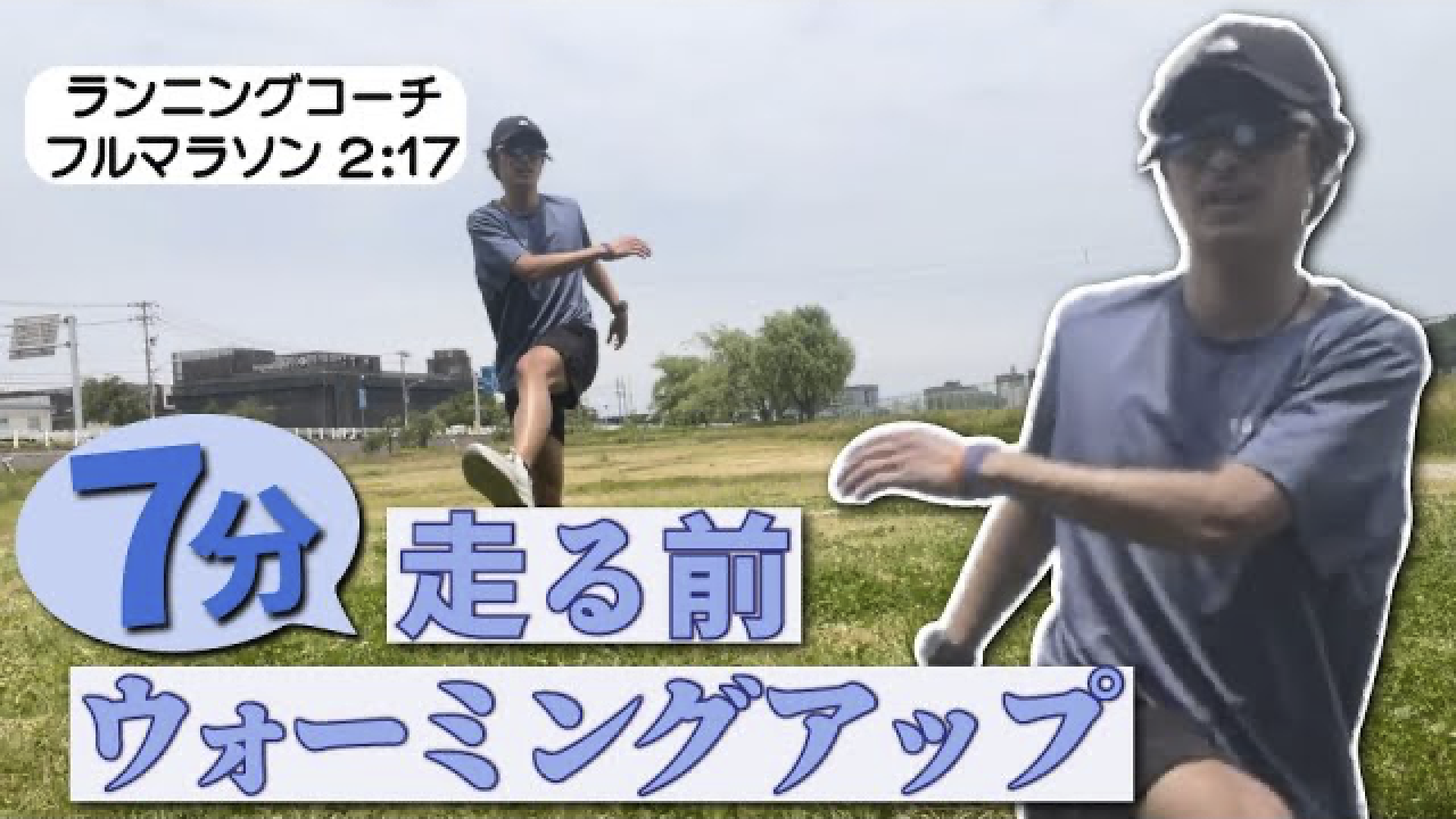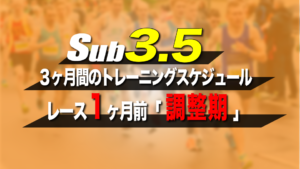サブ4達成のための4ヶ月間の練習【1•2ヶ月目基礎】
フルマラソンサブ4を達成したいけど…
・何度かチャレンジしたけど上手く達成できない
・正しいトレーニングがわからない…
・自分の年齢ではサブ4なんて無理なんじゃないか?
こう考えている人はいませんか?
当記事ではできるだけ簡単に分かりやすく、
かつ具体的に
サブ4達成までの
4ヶ月間のトレーニングプログラムを紹介します。
全3記事で構成します。
・4〜3ヶ月前の【継続】
・2ヶ月前の【ランニング】
・1ヶ月前の【調整】
の三構成です。
今回の記事では、
今まで運動をしたことがない方を対象にしています。
4ヶ月のうちの最初の2ヶ月間は運動に慣れることをテーマにします。
以下で詳しく解説します。
目次
サブ4って?
「マラソン サブ4」とは、
フルマラソン(42.195キロメートル)を
4時間未満で完走することのことです。
1km当たりのペースは、
約5分40秒から5分45秒程度で走る必要があります。
参考までにラップと通過タイムを記載します。
| 距離 (km) |
累積時間 (時:分:秒)
|
| 5 | 0:28:20 |
| 10 | 0:56:40 |
| 15 | 1:25:00 |
| 20 | 1:53:20 |
| 25 | 2:21:40 |
| 30 | 2:50:00 |
| 35 | 3:18:20 |
| 40 | 3:46:40 |
| 42.195 | 4:00:00 |
レース当日はこのタイムで走る必要があります!
走っていてペースがわからなくなる方も多いと思います。
ラップタイムがシールになって
手に貼れるアイテムもありますので
ご利用ください!
4〜3ヶ月前のテーマは【動き続けること】
サブ4もそうなのですが、
どのレベルのランナーにおいても言えることで、
フルマラソンを完走するうえで
毎日運動をする習慣の確保が大事となります。
頑張る体を作るために、頑張らないでも走れるようにする
マラソン当日は、
1km5分40秒で42km走り切る必要があります。
そのためには1km5分40秒で走れるスピードや
心肺機能を身につけなければいけませんし、
1回で42km走れる筋持久力や筋疲労耐性を身につけなかればいけません。
マラソン初心者が
いきなりこういった練習を行うのは
まず持ってこなせませんし、
怪我のリスクも高いです。
まずは、2ヶ月間かけて走ることに慣れて行きましょう。
この2ヶ月間は頑張る必要はありません!
とにかくラクにできるだけ距離を走れるように意識して行います。
具体的目標:週間走行距離60km
具体的な目標として、週間走行距離を用います。
1週間で走った(歩いた)距離の合計のことです。
2ヶ月後の週間走行距離は40km〜60kmが目標です。
徐々に徐々に週間走行距離を増やしていき継続的に走れる体を身につけます。
なぜ長く走れるようになるのか?
ゆっくり走る際には酸素を使ってエネルギーを生み出して体を動かします。
酸素を使うので有酸素運動と言います。
逆に速いペースで走る運動は、
酸素を使わずにエネルギーを生み出すので、
無酸素運動と言います。
酸素は、
筋中のミトコンドリアという
細胞でエネルギーに変換されるのですが、
長く走れる(長時間エネルギーを生み出す)ようにする必要があります。
ミトコンドリアは使えば使うほどエネルギー生産効率が高くなりますので
できるだけ使う=ゆっくり長く走る
ことでどんどんとミトコンドリアは成長し、
長く走れる体になっていきます。

具体的なトレーニングプログラム
| 4ヶ月前 | ||||
| 1週間目 | 2週間目 | 3週間目 | 4週間目 | |
| 月 | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 火 | ジョグ30分 | ジョグ30分 | ジョグ30分 | ジョグ30分 |
| 水 | ウォーク | ウォーク | ウォーク | ウォーク |
| 木 | ウォーク | ウォーク | ジョグ30分 | ジョグ30分 |
| 金 | ジョグ30分 | ジョグ30分 | ウォーク | ウォーク |
| 土 | ウォーク | ウォーク | ジョグ30分 | ジョグ30分 |
| 日 | ウォーク | ウォーク | ウォーク | ウォーク |
| 3ヶ月前 | ||||
| 1週間目 | 2週間目 | 3週間目 | 4週間目 | |
| 月 | 休み | 休み | 休み | 休み |
| 火 | ジョグ40分 | ジョグ40分 | ジョグ40分 | ジョグ40分 |
| 水 | ウォーク | ウォーク | ウォーク | ウォーク |
| 木 | ジョグ40分 | ジョグ30分 | 休orウォーク | 休orウォーク |
| 金 | ウォーク | ウォーク | ジョグ30分 | ジョグ30分 |
| 土 | ジョグ30分 | ジョグ50分 | ジョグ50分 | ジョグ60分 |
| 日 | ウォーク | ウォーク | ジョグ30分 | ジョグ30分 |
まずは一定のペースでゆっくり走ること
トレーニングのはじめの目標は「走ることに慣れる」「習慣化する」ことです。
まずは週に2回だけ30分のジョギングに取り組みましょう。
フルマラソンの目標ペースが1km5分45秒だからといって
そのタイムを気にしすぎてはいけません。
走るペースは気にせずゆっくり走ります。
ただ、ペースも何も決められていないと逆にどうやって走っていいかは難しいものです。
そのような方は、
アウトバック走でペースを考えながら
ランニングを行いましょう。
アウトバック走とは
河川敷などの
片道で長くとれる往復のコースを使用します。
「アウトバック走」は、
行きと帰りのペースを一定にするように走るトレーニングとなります。
例えば30分のジョギングであれば、
15分かけて河川敷を走ります。
15分が経過したら、
折り返してスタート地点まで戻ります。
この行きと帰りのペースが一定になるように
走るように心がけます。
・「行き」が速かった場合
→次回は「行き」のペースを落とします。
・「帰り」が速かった場合
→次回は「行き」からもう少しペースを上げます。
走らない日は「ウォーキング」
走らない日は同じ時間か、
もう少し長く50分程度「ウォーク」を取り入れましょう。
ゆくゆくは毎日でも走れるようにしたいので、
時間の確保や、
運動への耐性獲得のためにも、
ウォーキングで運動に慣れていきます。

2週間同じことをしたら少しレベルアップ!
2週を1サイクルとして、
徐々に走る頻度を増やしていきます。
2ヶ月目の最終サイクルでは一回で最大60分間走れるようにしたいと思います。

1週目は、筋肉痛や体の疲労を感じることが多いと思いますが、
2週目になると1週目の自分とは驚くほど疲労感は変わると思います。
1週目ひいひい言いながら行っていたランニングが、
2週目は気楽に行えます。
これが成長です!
トレーニング前の準備運動
トレーニング前には怪我の予防、
筋温の上昇、
呼吸を上げる準備のために準備運動を行います。
走る前に、
準備として心拍数を上げる必要があるので、
取り入れるべきは「ダイナミックストレッチ、バリスティックストレッチ」を取り入れましょう。
ストレッチには
- ・ダイナミックストレッチ
- ・バリスティックストレッチ
- ・スタティックストレッチ
の3つに分類されます。
このうちスタティックストレッチは運動前にはあまり推奨されていません。
運動前には「ダイナミックストレッチ、バリスティックストレッチ」を取り入れましょう。
ダイナミックストレッチとは
動的なストレッチ法で、
連続的な動きを使って筋肉を伸ばします。
例えば、ウォーキングランジ(前進しながらのしゃがむ)、
腕を大きく振るなどの動きが含まれます。
いわゆるラジオ体操のような運動のことをダイナミックストレッチと言います。
バリスティックストレッチとは
弾力的な動きを使って筋肉を伸ばすストレッチ法です。
バウンドやジャンプを使い、筋肉を素早く伸ばし戻します。
反動を使って大きく関節を動かすことをバリスティックストレッチと言います。
スタティックストレッチとは
静的なストレッチ法で、筋肉を伸ばしたまま一定のポジションを保持します。
例えば、脚を伸ばして前屈を行う、壁に寄りかかって腰を伸ばすなどがあります。
スタティックストレッチは筋肉の柔軟性を獲得するのには有効なストレッチですが、
一時的な筋力の低下も招いてしまうので注意が必要です。
以上を踏まえたウォーミングアップを動画で紹介しています。
走る前にぜひ取り入れてみてください。
毎日の練習時間を確保する方法
ここまでランニングのトレーニングについて解説しました。
ここまで記事を読んでいただければお分かりかと思いますが
基本は毎日のトレーニングとなります。
走る時間のみでも最低30分です。
準備運動や、ストレッチ、着替えの準備など考えると
走る時間以上に時間がかかります。
30分走るにも1時間は時間を要すると思います。
忙しい市民ランナーには毎日1時間
時間を作るのは相当な覚悟が必要です。

①通勤、退勤ラン推奨
会社まで走って通勤したり、
会社から自宅まで走って帰ることを
通勤ラン退勤ランと言いますが
ぜひ、この退勤ランを取り入れていただきたいと思います。
▼筆者も退勤ランを取り入れておりました▼
▼退勤ランに必要なこと準備するものはこちら▼
②練習会に参加する
参加しなければいけない練習会があれば
いやでも参加するようになるでしょう。

無料の練習会もいいですが、
無料であるがゆえにサボりがちです。
お近くのランニングクラブを探してください。
③結局はマラソンを生き甲斐にできるか
私も何人もランナーのサポートをしてきましたが、
みなさんやはりマラソンが「生き甲斐」になっているように思います。
趣味や楽しみではなく「生き甲斐」です。
結局のところ、
やりたいことに対して情熱がなければ
いくら時間があっても続かないんですよね。
逆を言えば、
時間がなくても情熱があれば、
どんなに忙しくても時間を作って走ります。
僕はそんな、ランニングを生き甲斐にしているランナーが集まるクラブを運営しています。
クラブに入部し、周りに感化されると言うのもとても有効な手段であると言えます。
▼まるお製作所RCはこちら▼
さらにステップアップ
次の1ヶ月はいよいよマラソンに向けてトレーニングとなります。
2ヶ月基礎のトレーニングを終えたら
こちらの記事をご覧ください!
その他の投稿